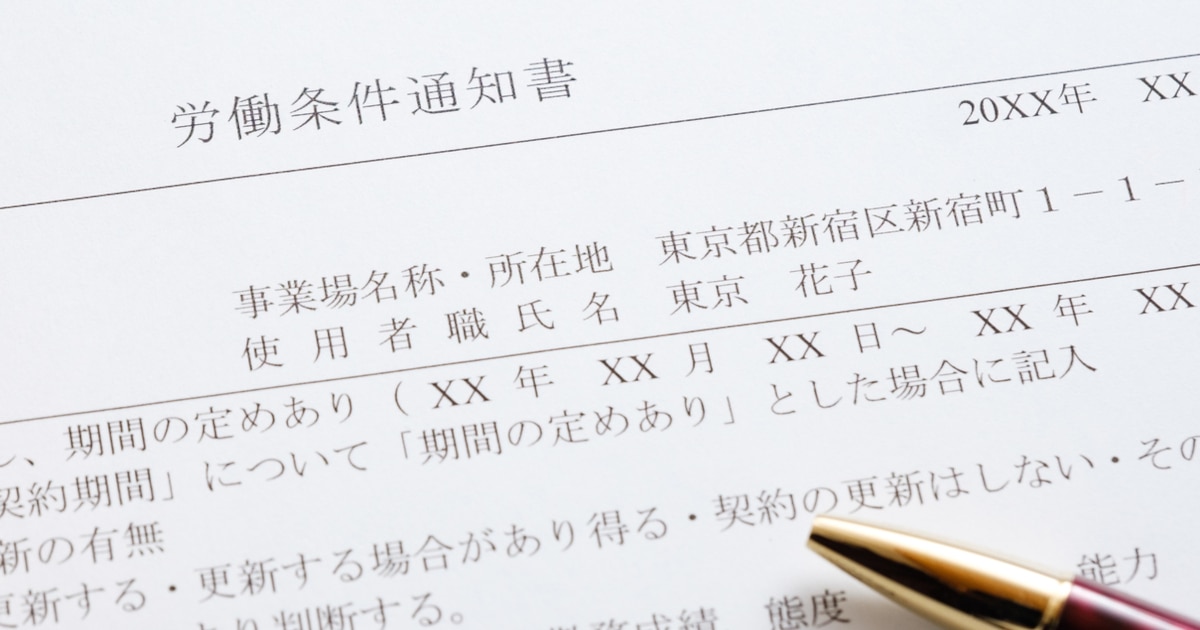
【雇用手続き】アルバイト・パートを雇用する際の必要書類を解説
近年、アルバイト・パートの数は増加傾向にあります。女性や65歳以上の高齢者が一定の割合を占めるなか、世帯主のアルバイト・パートもみられており、働き方の多様化が進んでいます。
特に人手不足が顕在化している職場では、新たな働き手の確保を目的として、アルバイト・パートの積極的な雇用が期待されています。
そのようななか、アルバイト・パートをはじめとした非正規雇用にあたって、必要な書類や提出物について準備を始めている人事・労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、アルバイト・パートを雇用する際に必要な書類について解説します。
出典:厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法のあらまし』
法律で定められた必要書類
アルバイト・パートの雇用にあたって、法律で事業主に作成が義務づけられている書類があります。雇入れ後のトラブルを防ぐためにも、事業主には法令を遵守した対応が求められます。
①労働条件通知書
アルバイト・パートを雇用する際は、労働契約の締結や条件について明示した労働条件通知書を作成して、交付する必要があります。
この労働条件通知書による労働条件の明示は、『労働基準法』第15条と『短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律』(以下、パートタイム・有期雇用労働法)第6条によって規定されています。
▼労働基準法第15条
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』第15条
▼パートタイム・有期雇用労働法第6条
第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。
引用元:e-Gov法令検索『パートタイム・有期雇用労働法』第6条
原則として書面での交付が必要とされていますが、従業員が希望した場合には、電子メールやFAXでの送付も認められています。
なお、労働条件通知書は、全従業員に共通した内容ではなく、従業員一人ひとりに対して給与・契約期間・業務などの提示が必要です。
労働条件通知書に明示が必要な事項として、以下が挙げられます。
▼労働基準法上の明示事項
- 労働契約の期間に関する事項
- 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
- 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金、賞与その他これらに準ずる賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
引用元:厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法のあらまし』
▼パートタイム・有期雇用労働法上の明示事項
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
※違反の場合は 10 万円以下の過料に処せられます。
引用元:厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法のあらまし』
出典:厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法のあらまし』/e-Gov法令検索『労働基準法』『パートタイム・有期雇用労働法』
②マイナンバーが記載された書類
事業主がアルバイト・パートを雇入れる際、雇用保険の申請・届出時には従業員のマイナンバーを記載することが義務づけられています。
▼マイナンバーの記載が必要な書類
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
従業員には、マイナンバーカードの提示か、マイナンバーが記載された書類の持参を依頼します。記載された書類からマイナンバーを取得する際は、なりすまし防止のための身元確認も必要です。
▼マイナンバーが記載された書類
- 個人番号通知カード
- 個人番号記載された住民票(住民票記載事項証明書)
なお、届出の際にマイナンバーに関する書類の写しを添付する必要はありません。
出典:厚生労働省『雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。』
作成が望ましい書類
アルバイト・パートは、個々の事情に応じて労働時間や業務、給与形態などが設定されています。
働き方が異なる従業員との認識の相違を防いで、雇用後のトラブルを避けるために、作成したほうがよい書類があります。
ここでは、法律上の義務はありませんが、作成が望ましい書類を3つ取り上げます。
①雇用契約書
雇用契約書とは、雇用契約が締結されたことを証明する書類です。
労働条件を記載して、事業主・従業員が署名・捺印をすることで、双方合意のもと雇用契約が成立したことを証明できます。
作成・交付が義務づけられている労働条件通知書と合わせて、“労働条件通知書 兼 雇用契約書”として作成・交付することも可能です。
法律上の義務はないものの、作成が望ましいとされる雇用契約書については、こちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
アルバイト・パートの雇用契約書とは? 労働条件通知書の違いとともに解説
②誓約書
誓約書は、企業の方針や就業規則などを遵守することを従業員に同意してもらうための書類です。
会社の規定を遵守することに同意した証拠を書面によって残すことで、先々のトラブルを防止する目的があります。誓約書に記載する内容としては、就業規則の遵守や個人情報の取扱い、SNSでの情報発信などのルールが挙げられます。
③各種申請書・証明書
雇用後に給与の振り込みや手当の支給を行う、または虚偽申告のトラブルを防止するために、従業員に申請書・証明書を提出してもらうこともあります。
▼従業員に提出してもらう申請書・証明書
- 給与の振込口座の登録申請書
- 交通費と通勤経路の申請書
- 資格や免許に関する証明書
社会保険・税金に関する必要書類
アルバイト・パートとして働く従業員が一定の条件に該当する場合、社会保険の加入対象になったり、税金の控除が受けられたりします。
事業主は、従業員を雇入れる際に、社会保険や税金に関する手続きを適切に行うことが重要です。
ここでは、社会保険・税金に関する書類について解説します。
①健康保険・厚生年金保険の加入書類
事業主は、常時雇用する従業員に対して、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入手続きを行います。
アルバイト・パートの場合は、1週の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上という条件を満たす場合に、被保険者となります。
社会保険の加入手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
事業主が日本年金機構に提出する書類 |
従業員に提出を求める書類 |
|
|
出典:厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法のあらまし』/日本年金機構『就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き』
②雇用保険の加入書類
事業主は、従業員を雇用する際に雇用保険に加入する義務があり、指定の書類をハローワークに届ける必要があります。
▼事業主がハローワークに提出する書類
- 雇用保険の加入申請書(雇用保険被保険者資格取得届)
- 賃金台帳
- 労働者名簿
- 出勤簿・タイムカード
- そのほかの社会保険の資格取得関係書類
- 雇用期間を確認できる資料
ただし、雇用保険の被保険者となるには、雇用期間や所定労働時間の条件を満たさなければなりません。
出典:厚生労働省『事業主の行う雇用保険の手続き』『雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!』『手続き一覧表』
③年末調整・所得控除に関する書面
アルバイト・パートを雇用する際は、年末調整や所得控除に関する書類の提出を求める必要があります。
年の途中で雇用した従業員が前職で給与の支払いを受けていた場合は、その給与も含めて年末調整を行います。
また、年末調整を行う際は、給与所得から基礎控除や扶養控除などを計算するための書類が必要です。
▼従業員に提出を求める書類
- 源泉徴収票(ほかの会社から交付されたもの)
- 扶養控除等申告書
- 基礎控除申告書
- 配偶者控除等申告書および所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
出典:国税庁『No.2674 中途就職者の年末調整』『令和3年分 年末調整のしかた』
まとめ
この記事では、アルバイト・パートの雇用時に必要な書類について、以下の項目を解説しました。
- 法律で定められた必要書類
- 作成が望ましい書類
- 社会保険・税金に関する必要書類
アルバイト・パートを雇用する際は、法令で義務づけられた書類をはじめ、社会保険の加入、年末調整や控除の手続きのためにさまざまな書類が必要です。
従業員とのトラブルや法令違反を防ぐために、事業主が用意する書類、従業員に提出を求める書類について雇用前に確認しておくことが大切です。
なお、アルバイト・パートは個々の労働条件が異なるため、労務管理が煩雑化しやすいといった課題もあります。
雇用時に定めた労働時間や勤務日数、収入の上限など、個別条件に対応したシフトを作成するには、『シフオプ』の活用が有効です。詳しい機能についてはこちらをご確認ください。
また、アルバイト・パートの採用基準に関する記事はこちらで解説しています。併せてご確認ください。







